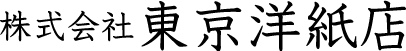里山 それはどこか懐かしい響き 知っているようで 知らない
知らないようで 親しみのある場所
里山とは どこにある どんな場所なのか
田んぼに畑、小川やあぜ道、どうやら特別なものではなさそうです。でも、記憶や体験を語ってくれる人々のお話に、なぜか引き込まれていきます。さっそく、お一人目のお話をきいてみませんか!
第3回 岩間敏彦氏に聞く
―日本人は里山からたくさんの恵みを受け取ってきましたが、一方では「手つかずの自然こそが自然のあるべき姿だ」「木は伐るべきではない」等の潜在意識も持っているように思われます。そのような意識の壁をどう変えてゆけるでしょうか。―
緑が残っているから大丈夫だと安心せず、実際に森の中に入ってみてほしいですね。そうすると、とんでもないことになっているのがわかります。木がバタバタと倒れていたり、竹林に覆われていたり、地滑りが起きていたりと一見豊かに見える森でも、中は大変なことになっているんです。反対にきちんと整備されている森も見てほしいですね。そうすると人間が自然とかかわりを持つことの大切さが見えてくると思います。
―里山や森林をあまり知らない私たちを感化してくれるような、岩間さんオススメの本はありますか。―
ぼくらがバイブル的に読んでいる本があります。レイチェル・カーソン女史の『センス・オブ・ワンダー』という本です。里山が舞台ではないのですが、あらゆるヒントとなる本です。例えば、大人と子どもが森で過ごせば、大人は忘れかけていた五感を取り戻すきっかけになるといったことが書かれています。また、世界中の子どもが生涯にわたり消えないセンス・オブ・ワンダー(=神秘さや不思議さに目をみはる感性)を授かれば、大人になるとやってくる怠慢と幻滅、人工的なものに夢中になることに対する解毒剤にもなるといったことも書かれています。
これを読んでいて、里山を思い出しました。里山は、お膳立てされた場所へ遊びに行くのとは違って、自分がクリエイティブにならないとつまらない場所です。逆にクリエイティブになれれば、なんでも遊びに結び付けられる素晴らしい場所です。『センス・オブ・ワンダー』を読んでから里山に行けば、きっとすぐ、里山の魅力に気付けると思いますよ。
里山で楽しむ、里山を楽しむ
―ビギナーでも楽しめる里山遊びはありますか。―
里山ガールですよ!籐のバスケットなどの中にマイボトルとかお茶のセット、手作りサンドイッチなどを入れて、里山ピクニックに行き、見晴らしいいところでランチを楽しむと気持ちいいですよ。また、里山は低い山であることが多いので、歩きやすいんです。それに、山一つ越えればいっぺんに景色が変わることもあります。ピクニックで発見した鳥や花をみんなで調べて、共有するおもしろさもありますね。メカ好きの男性にとっても、里山はいい遊び場です。たとえば頑丈な三脚にフィールドスコープとデジカメをセットして、野鳥を追いかける人がいます。結構かっこいいんですよ。
里山で遊ぶというと、どうしても遠足やハイキングの延長と考えてしまいがちですが、里山ではそれぞれのセンスに合わせ色々な楽しみ方ができます。室内でやることを里山でやっちゃうのも楽しいです。たとえば緋毛氈(ひもうせん-赤いフェルト地の敷物)を敷いて、本格的にお茶をたてるとか。雨の日は雨の日で、ちょっといい合羽着て、雨の日の散策を楽しむのもいいですね。いずれにしてもクリエイティブになることが大切です。とはいっても突然そうなるのは難しいから、まずは提供されたメニューを体感してみるのもいいでしょうね。
―なんだか楽しそうですね~。里山ガール!となれば里山ボーイも!? 何となく登山に近いイメージがあるので構えていたのですが、里山って低い山が多いのですね。私も行って楽しめそうな気がしてきました。雨の日の散策なんて、「雨」と聞くだけでインドアを考えそうですが、そうではないんですね。今度、近くの里山を調べてみたいと思います!!クリエイティブなれるかどうかは?ですが(笑)―
熊本県山都町―これまでに岩間さんは何か所くらいの里山に行かれているのですか―
住んでいる大磯自体が里山なんです。里山はつながっているので、何か所という表現が難しいですね。あえていうなら九州から北海道まで、様々な地域の里山を訪ねています。地域によって特徴もあるんですよ。例えば九州なら、ものすごく急峻な地形に石垣を積んで作られた棚田があります。とてもダイナミックな風景なんですよ。
里山というと「田畑と雑木林があって」と思いがちですが、阿蘇山も立派な里山なんです。里山の定義自体が曖昧ということはありますが、環境省では、二次的な草原も人がかかわることで生物多様性が豊かになっている場所として里山に定義しています。阿蘇では春になると草原の野焼きをしています。これは山全体を焼いて木が生い茂るのを防ぎ、草原の芽生えを助けるんです。人々はそこをあか牛などの放牧場として活用するんですね。あか牛は食べちゃうんですけどね(笑)。でも、そんな人の営みによって草原が守られて、草原ならではの豊かな生態系も守られているんです。
北海道の里山というと、関東とは利用形態が違うようです。薪を得るために山から木を伐るけれども、手入れをして永続的に薪を得ようとは考えてこなかったようですね。おそらく木はいくらでもあるからでしょう。一方で原点を辿れば、アイヌ民族の伝統が見えてきます。アイヌの人たちは、すべてを自然から得ていましたが、自然のすべてに神が宿るとして、神から分けて頂くという形で自然と共生してきたそうです。この伝統はぜひ学んでほしいですね。
―私たちにとってなじみ深いお祭りと、アイヌ民族の文化には共通性がありそうですね。―
日本には自然信仰が根強く残っています。今でも受け継がれている多くのお祭り、特に五穀豊穣のお祭りはどれも里山で生まれたものです。地域によって微妙に内容は変わってきますが、どれも趣旨は似ています。
今森光彦さんも取材されていますが、「虫送り」という面白い行事があります。豊作祈願と害虫駆除のお祭りです。たいまつで火を焚き、わら人形を作って悪霊をかたどり、害虫をくくりつけて鉦や太鼓をたたきながら、川に流すというものです。この虫送りは日本全国、様々な形で行われてきましたようですが、農薬が普及した今ではなくなりつつあります。また、田植え中や耕作中にどうしても殺してしまう虫を供養する「虫供養」というお祭りもあるそうです。
―現在、自然農法のように害虫、益虫という概念を超えて、ただ自然のままの生態系のシステムに任せて農業を行うという方法もありますが、伝統的な里山における農業とは考え方が異なるのでしょうか。―
基本的には同じだと思います。生態系の中では様々な虫や生き物がいて、天敵関係があるので、相互に影響し合っている。その中で作物を育てるというのが、本来の農業だと思います。ところが「楽に実りを多く、高収穫に」という概念が生まれてから農薬が使われるようになりました。
また、「台風にも耐えられるような強いイネを」と考えて品種改良するといった具合に安定的な収穫を求めはじめたことで、どんどんと自然とかけ離れてしまったと感じています。農薬を使うことも、化学肥料を使うことも、自然に対する畏敬の念が薄れていることを表していると思うんです。
―何も意識せずに普段の生活を送ってきましたが、これを機会に里山ピクニックを実践してみながら、今回伺った内容をしっかり見つめていきたいと思います。長い時間ありがとうございました。たいへん勉強になりました。―
里山 それはどこか懐かしい響き 知っているようで 知らない
知らないようで 親しみのある場所
里山とは どこにある どんな場所なのでしょうか・・・
東京に事務所を置く私たち東京洋紙店のメンバーの中でも里山についての知識は個々様々です。今回岩間さんからお話を伺い、そのポイントが見えてきたような気がします。これまで里山は日本人の暮らしにあまりにも身近な存在であったがゆえに、その価値は見過ごされてきました。しかし、次の世代に何を残すのかを考えるとき、その大きなヒントは、各地の気候風土の中で生まれ受け継がれてきた里山での暮らしの中にこそ見出せるように思うのです。
さて、次回は、宇都宮大学/農業学部附属里山科学センター 髙橋俊守準教授にご登場頂きます!!11月上旬UP予定です。お楽しみに!!